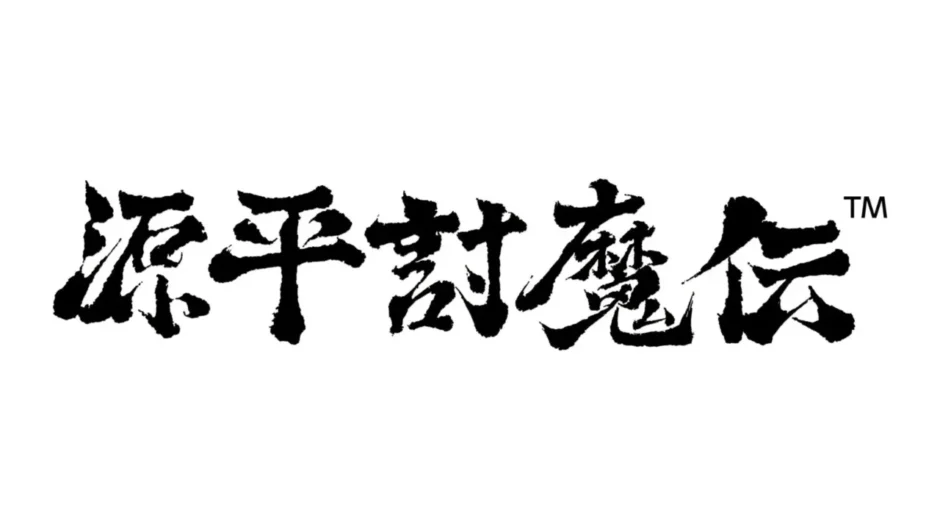アーケードゲーム『源平討魔伝』は、1986年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)が開発・発売した横スクロール・ハック&スラッシュ系アクションゲームです。プレイヤーは壇ノ浦で討ち死にした平景清を操作し、三種の神器を集めて魔界源氏の頼朝を討つべく鎌倉へ向かいます。特徴としては、横スクロール・ビッグモード・平面モードの3モードを持ち、多彩な演出や大迫力のボス戦、和風グラフィックと音声が評価されました。
開発背景や技術的な挑戦
本作は当初、開発スタッフ数名が勤務時間外に草案として制作を進めており、その後当時のナムコ社長・中村雅哉氏に高く評価され、正式にプロジェクトとしてスタートしました。タイトルロゴも中村氏の筆によるものです。技術面では、当時のアーケード基板「System 86」の性能をフル活用し、8方向レバー+2ボタンで3つの異なる視点をスムーズに切り替える高度な演出が実現されました。また、ボイスサンプルや大きなスプライト表示、多重スクロールなども当時としては驚異的な表現です。
プレイ体験
ゲームは難易度が高く、ボス戦では義経、弁慶、頼朝といった史実のキャラクターが立ちはだかります。三種の神器収集のためにステージ分岐を正しく進む必要があり、やり応えのある探索要素も魅力的です。慣れてくると計画的なルート選択と回避行動が重要になり、特に平面モードでの緊張感やビッグモードでの迫力あるアクションは強く記憶に残ります。和風BGMとボイスが雰囲気を盛り上げて、クセになるプレイ体験を提供します。
初期評価と現在の再評価
『源平討魔伝』は、1986年にナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント)からアーケード向けにリリースされたアクションゲームです。平安時代末期の源平合戦を題材にしており、独特の和風世界観と高難易度のゲームプレイが特徴です。総合的な評価としては、ポジティブな意見が約70%、ネガティブな意見が約30%と、好意的な評価が多い作品となっています。
ポジティブな評価の要因として、まず挙げられるのは、純和風の世界観と緻密に描かれたグラフィックデザインです。日本的な装いを持ったアクションゲームは当時としては珍しく、背景やキャラクターデザインがプレイヤーを魅了しました。また、ゲーム内で使用される音楽や効果音も和風テイストが強調され、作品全体の雰囲気作りに貢献しています。さらに、ゲームシステムの多様性も高く評価されています。プレイヤーは、横スクロール、トップビュー、ビッグモードと呼ばれる3つの異なる視点でステージを進行し、それぞれのモードで異なる操作感や戦略が求められます。このような多彩なゲームプレイが、プレイヤーに新鮮な体験を提供しています。
一方、ネガティブな評価の要因として、ゲームの難易度の高さが挙げられます。特に、京都以降のステージでは、ゲームオーバー時にコンティニューができない仕様となっており、プレイヤーにとって大きな挑戦となっています。また、一部の敵キャラクターの攻撃パターンやトラップが理不尽と感じられることもあり、これがストレス要因となる場合もあります。
本作は、和風の世界観や高難易度のアクションゲームを好むプレイヤーにおすすめです。特に、歴史的な題材や独特のビジュアルデザインに興味がある方には、魅力的な作品と言えるでしょう。ただし、その難易度の高さから、初心者やカジュアルなプレイヤーには敷居が高いかもしれません。攻略情報を参考にしながらプレイすることで、より深くゲームを楽しむことができるでしょう。
他ジャンル・文化への影響
日本の和風アクション作品としての先駆けとなり、その後の『サムライ』『和風ホラー』系ゲームに影響を与えました。須田剛一氏も本作を高く評価しています。主人公景清はナムコ作品やコラボ作品にも登場する人気キャラクターとなり、サントラ収録やグッズ展開などでも文化的価値を持ち続けています。
リメイクでの進化
もし現代にリメイクされるとすれば、高解像度&滑らかなアニメーション、多彩な視点切替オプション、オンライン協力プレイ、追加ストーリーやアレンジモードの導入などによって、オリジナルの良さを活かしつつ新規ファン層へも訴求できる作品になるでしょう。
まとめ
1986年にナムコが放った『源平討魔伝』は、和風モチーフと高難易度、3モード構成によって独自の存在感を放つアーケードアクションです。当時の技術力の粋を集め、完成度の高さと遊び込み要素によって多くのプレイヤーを魅了しました。家庭用移植や復刻版も多数展開され、今なお再評価され続けています。もし未プレイなら、ぜひ当時の緊張感と演出を体験してみてください。
攻略
プレイヤーは、壇ノ浦の戦いで命を落とした平家の武将・平景清となり、「ぷれいや」たる自らの供物によって地獄から蘇り、3種の神器を集めたうえで宿敵・源頼朝を討つために鎌倉を目指すことになる和風怪奇アクションゲーム『源平討魔伝』を操作します。本作は1986年にナムコがアーケード向けにSYSTEM 86基板でリリースした作品で、横スクロールの「小モード」、巨大キャラクターとの戦いが展開する「BIGモード」、および上空から見下ろす「平面モード」の3つのモードをステージごとに切り替えながら攻略していく構成で、それぞれに異なる操作感やルート選択の楽しさがあるという革新的なデザインが魅力です。操作は8方向レバーと剣攻撃とジャンプの2つのボタンで行い、時には分岐する鳥居を通ることでルートが変化して神器のあるステージへ導かれたり、黄泉の国やお釈迦様が玉を落とすボーナスステージ、さらにはユーモラスな「だじゃれの国」など、多彩な演出とステージ構成が楽しめます。ライフは画面上に蝋燭で示され、敵の攻撃や障害物に触れると蝋燭が減り、これがすべて消えるとゲームオーバーとなり、プレイヤーは黄泉の国に落ちて閻魔による裁きに直面し、運命のつづらを開けて復活(“生”)か即ゲームオーバー(“死”)かを運に任せる展開もあります。3種の神器は草薙剣、八咫鏡、八尺瓊曲玉の3つで、それぞれ攻撃力上昇、特殊攻撃無効、毒無効などの能力を持ち、ラスボス攻略に欠かせない存在です。こうして全ての神器を集めたうえで鎌倉にたどり着き頼朝を倒すのがプレイヤーの最終目的であり、ゲームオーバーはライフ(蝋燭)がゼロになるか、黄泉の国で“死”を引いてしまった場合に訪れます。
ステージ
全ステージの特徴を紹介し、それぞれのステージでの攻略ポイントや難所について解説していきます。
| ステージ | モード | 概要 |
|---|---|---|
| 地獄1 | 横 | ゲームスタートと同時に、後ろから骸骨と要石が迫ってきます。要石をやりすごしたら骸骨を処理しましょう。要石は斬りつけると剣力が落ちることを覚えておきたいです。最初は梅筋骨との混合攻撃に手を焼きますが、剣を振るタイミングとジェネレータを優先的に壊すコツを掴めば楽に進めるはずです。銭の余裕があれば、要石に注意して剣アイテムを入手しましょう。2つある鳥居の行き先は同じです。 |
| 地獄2 | BIG | 2種類の敵が登場します。初めてのBIGモードであるためチュートリアル感覚で操作感を体感できます。 |
| 長門 | 平面 | 小さな敵に接触しないよう注意し、大独楽は衝撃波で倒しましょう。つづらは剣で切ると銭と命が手に入ります。最後の鳥居は石見・周防・豊前に分岐します。 |
| 豊前 | BIG | スタート時に待ち、虎を倒すと般若だけになります。義経は小刀を投げてきますので、ジャンプ斬りで頭を狙いましょう。 |
| 豊後 | 横 | 火牛の集団を倒すと命が回復します。尺取虫は銀を斬りながらジャンプで避けましょう。要石に注意し、上に飛び乗って進みます。 |
| 伊予 | BIG | 猿に注意し、ジェネレーターを叩くにはジャンプが必要です。弁慶は猿を無視し、すくい斬りで倒しましょう。 |
| 讃岐 | 横 | 大百足に乗り、小島へジャンプして進みます。要石を超えると雷神とトンビが出現するので、高台から倒して蠟燭を取りましょう。 |
| 安芸 | 横 | 難易度が高く、障害物が多いステージです。後ろから来る要石を避け、巻物を取りましょう。剣アイテムを取ると後の展開が楽になります。 |
| 周防 | BIG | 豊前に似た雰囲気で、虎を処理して進みます。飛んでくる欠を振り下ろしで叩き落とし、義経に近付くコツは小刀を使い、間合いを詰めます。 |
| 備後 | BIG | 蛙が登場し、ダメージを与える敵です。ジェネレーターから登場する蛙を振り下ろしで処理し、弁慶をかぶと割りで倒しましょう。 |
| 備前 | BIG | 虎を処理し、進んでいくステージです。BGMが変わると琵琶法師が出現します。振り下ろしで兎と蛙を確実に倒しましょう。 |
| 備中 | 横 | 最後の鳥居を目指す難易度の高いステージです。要石を避けて進み、左右の間隔が狭い地面に注意。 |
| 播磨 | 横 | 最後の鳥居から摂津へ進むステージです。竜を高台を活用して倒します。 |
| 石見 | BIG | 虎と義経を倒すステージです。義経は頭に効率良く刀を当てて倒します。 |
| 出雲 | 横 | 落とし穴を避けて進むステージです。火牛と餓鬼が登場するため注意が必要です。要石に乗ってやり過ごすこともできます。 |
| 因幡 | 横 | 骸骨船に乗って進むステージです。風神と骸骨船を倒し、要石の上の鳥居に入って美作に進みます。 |
| 伯耆 | BIG | 骸骨と毒キノコに注意しながら進むステージです。弁慶を倒すにはすくい斬りを駆使しましょう。 |
| 但馬 | BIG | 草で足元が見えにくいステージです。虎と琵琶法師に注意し、確実に敵を倒して進みます。 |
| 丹後 | 横 | 竜と狛犬に注意し、確実に倒して進みます。 |
| 丹波 | 横 | 細かいジャンプ操作が必要なステージです。要石からのジャンプや大百足の上から要石へのジャンプが攻略のポイント。 |
| 山城 | BIG | 義経と戦うステージです。矢を叩き落とし、義経の隙を見逃さないように戦います。 |
| 京都 | 平面 | ルートが3分割し、迷路状のステージです。鳥居の分岐点に注意しながら進みます。 |
| 大和 | BIG | 鉄球が登場するステージで、義経との戦いもあります。鉄球を避けながら義経を倒しましょう。 |
| 伊勢 | 横 | 多数の落とし穴と要石がある難しいステージです。入手の難易度は高いですが、八尺瓊勾玉があります。 |
| 尾張 | BIG | 鳥居までの距離が短いステージで、義経との戦いがあります。 |
| 三河 | 横 | 敵が出現しないステージで、落とし穴と要石に注意しながら進みます。 |
| 遠江 | BIG | 曲玉の有無で難易度が変化。毒キノコに注意し、ジェネレーターを破壊しながら進みます。 |
| 伊賀 | BIG | 弁慶が新たな攻撃パターンで登場。棒の攻撃を避けつつ、すくい斬りで倒します |
| 近江 | 横 | 蛾を倒しながら進みます。ジャンプを使いつつ小島を渡りながら進みます。 |
| 美濃 | BIG | 義経と洞窟で戦います。大百足は無視し、義経との戦いに集中します。 |
| 信濃 | 横 | 草薙剣が入手できます。三首竜は、頭が弱点。 |
| 若狭 | BIG | ステージ開始直後の虎は注意が必要。義経は山城と同じパターンで攻めてきます。 |
| 加賀 | BIG | 難易度は高くありません。義経が登場。 |
| 越前 | 平面 | 最長のステージ。八咫鏡が隠されています。ワープゾーンを利用して越中から信濃に抜けられます。迷路のような構成で、敵の瓢箪に注意が必要です。八咫鏡を入手するまではワープゾーンを利用しないことがポイントです。 |
| 越後 | 横 | 小島や要石はジャンプで届く距離に配置されています。狛犬を倒してから佐渡への鳥居を目指します。 |
| 上野 | BIG | 雷を出すジェネレーターがあり、八咫鏡がない場合は雷を避けるか、ジェネレーターを早く破壊して進むことが重要です。 |
| 甲斐 | BIG | 鉄球トラップに注意しながら進む必要があります。弁慶との戦いでは、すくい斬りを狙います。草難剣を持っていると有利。 |
| 駿河 | 横 | 小島の動きを把握しながら進みます。 |
| 武蔵 | 平面 | 神器が揃っていない場合、トラップ鳥居を活用して不足している神器の回収を再チャレンジします。最初の鳥居から相模に移動できます。 |
| 相模 | BIG | 弁慶と義経の双璧と戦うステージ。スタート時には弁慶の出現を待ち、登場後、かぶと割りを狙って撃滅します。義経と戦う前に、鉄球トラップが待ち構えています。難所は上下に動く鉄球と振り子状に動く鉄球が重複している場面です。鉄球の動きと景清に当たらないポイントを探しつつ、義経を戦います。 |
| 鎌倉 | BIG | 三種の神器をすべて持たずに鎌倉に到着すると、頼朝にダメージを与えられず景清の負けが決定します。頼朝は3回の変身を遂げます。最初は攻撃せず、上から雷が襲ってきます。頼朝の顔が一変し、般若の面になると攻撃が開始。最終的に頼朝は石像となり、攻撃を繰り出します。 |
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 1986