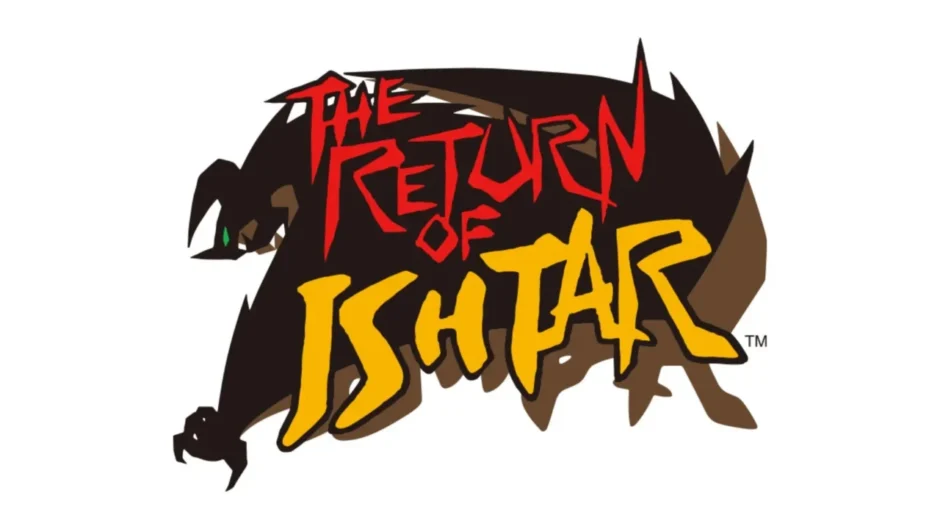アーケード版『イシターの復活』は、1986年7月にナムコ(開発: ゲームスタジオ)から稼働開始されたアクションRPGです。ジャンルはアクションRPGで、2人同時プレイや探索要素、成長要素、パスワード継続システムなどを特徴としています。プラットフォームはまずアーケードですが、その後PC-8801mkIISR以降、PC-9801、X68000、X1turbo、FM-77、MSX2、Windows、iアプリ、EZアプリ、Wiiのバーチャルコンソール、PlayStation 4やNintendo Switch(アーケードアーカイブス版)といった幅広い機種へ移植・配信されました。
開発背景や技術的な挑戦
『イシターの復活』は『ドルアーガの塔』(1984年)の続編として構想され、アーケードにおける新しいRPG体験を実現しようとしました。開発には遠藤雅伸氏が深く関与し、シナリオ・デザインの方向性を決定しています。基板にはナムコ・システム86を採用し、解像度288×224ピクセル、パレット4096色という当時としては先進的な仕様を用いました。加えて、アーケードゲームで初めてパスワードを導入し、長期的なプレイを可能にした点は大きな挑戦でした。一方、移植版ではSPSなどがPC-8801、PC-9801、X68000などの日本のパソコン機向けに調整を施しました。ハードの制約からアーケード版の滑らかさを完全に再現することは困難でしたが、忠実な雰囲気を残しつつ家庭でじっくり楽しめるよう工夫されています。
プレイ体験
本作ではプレイヤーがカイとギルガメスを操作し、2人で協力して塔からの脱出を目指します。カイは魔法を主体に遠距離攻撃を担い、ギルガメスは剣で敵を防ぎ前線を支えるという役割分担がありました。特に画面スクロールがカイに依存しているため、ギルガメスが画面外に追いやられる場面があり、互いの位置関係を調整しながら進む必要があるのが大きな特徴です。
家庭用やPCへの移植によって、アーケード版の制限を超えて繰り返し挑戦する環境が整い、プレイヤーはじっくり探索や成長要素を味わえるようになりました。ただし、移植によって敵の挙動やスクロール処理が簡略化されたため、アーケード版特有の緊張感が一部失われることもありました。
初期の評価と現在の再評価
稼働当初、本作は「アーケードで本格的なRPGを遊ぶ」という新しさから注目を集めましたが、前作『ドルアーガの塔』と比較すると人気や話題性はやや限定的でした。『ドルアーガの塔』が社会現象ともいえる攻略ブームを巻き起こし、ゲーマー同士の情報交換文化を生んだのに対し、『イシターの復活』は難易度の高さや2人協力前提の構造が一部のプレイヤーにとって敷居となり、広範囲の支持を得るには至りませんでした。
しかしながら、後年の再評価では、パスワードによる進行継続や協力プレイの本格導入など、アーケードRPGの可能性を示した作品としての価値が見直されています。単に『ドルアーガの塔』の続編に留まらず、システム面で革新を試みた異色作として独自の地位を築いています。
他ジャンル・文化への影響
『イシターの復活』は、アーケードでRPG的要素を導入した先駆的存在であり、後のアクションRPGや探索型ゲームに影響を与えました。特に「役割の異なる2人のキャラクターを操作する協力型ゲームデザイン」は、後続のマルチプレイやRPGタイトルに受け継がれています。また、家庭用やPCへの移植が比較的早期に行われたことで、広範なゲーマー層に触れる機会を提供し、日本のRPG文化の拡大に寄与しました。
リメイクでの進化
アーケード版そのもののリメイクは行われていませんが、家庭用移植や再配信において様々な進化を遂げました。『ナムコミュージアム VOL.4』(PlayStation)では、裏面モードといった新要素が追加されました。さらにPlayStation 4とNintendo Switchで配信された「アーケードアーカイブス」版では、オリジナルの挙動を忠実に再現するモードと遊びやすさを考慮した設定を切り替えられるようになり、プレイヤーの好みに合わせた体験が可能になっています。
特別な存在である理由
『イシターの復活』は、アーケードで遊ぶRPGの新しい方向性を提示した点において特別な存在です。2人協力プレイやパスワード継続システムといった仕組みは、当時のアーケードゲームにおける常識を超えたものでした。前作ほどの爆発的な話題にはならなかったものの、独自の試みを貫いた作品として、今もレトロゲームファンから評価されています。
まとめ
アーケード版『イシターの復活』は、『ドルアーガの塔』の続編でありながら、単なる追随ではなく新しいシステムや協力プレイを導入した意欲作です。前作の大ヒットと比べると知名度や人気の面で劣る部分もありましたが、革新的な要素を多数盛り込み、後のアクションRPGの発展に寄与しました。家庭用やPCへの移植を通じて長く遊ばれ続けてきたことも、本作の存在感を強調しています。派手さよりも独自性で語られる作品として、今なお注目に値する一作です。
©1986 Namco